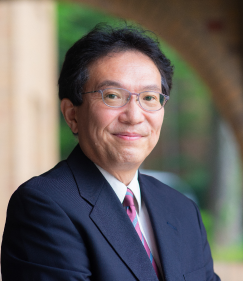
東京大学大学院情報理工学系研究科・電子情報学専攻 教授
伊庭 斉志 氏
PROFILE
01
進化と知能の創発の研究を手掛ける

―伊庭先生の研究領域はかなり幅広いです。現在取り組まれている研究の概要をご紹介いただけますでしょうか。
私は1980年代の中頃からAIの研究をして来ました。何度かの冬と春も直接・間接的に経験しています。その後人工生命の研究にも着手し、現在は主に生命現象に基づいて進化や知能の創発(個々の要素の相互作用が全体に影響を与えて新たな概念や現象が生み出されること)、人工生命を中心としたAIを研究しています。最近では生成AIにおける最適化に取り組んでいます。応用としては、ヒューマノイドロボット(人型ロボット)や金融、ゲームAI、あとは医療分野やセキュリティの画像解析を企業の方と一緒に進めています。
―伊庭先生は生命に基づいたものをAIで結び付けておられます。AIがどうやって考え方を進化させていくのですか。進化計算(生物進化のメカニズムによって、最適化問題を解決するアルゴリズムの総称)という部分で、自動的に計算していくようなものなのでしょうか。
そうですね。進化計算というのは一つの考え方です。最近では群知能(個々の構成要素がシンプルなルールに基づいて行動することによって、全体として高度かつ複雑な問題を解決する能力を持つ現象)と言って群れが集団全体で問題を解く手法もあります。例えば蜂とか蟻みたいにです。そういう生物がある程度賢く振舞って生き残るので、その賢さをAIや機械学習の最適化の部分に応用するという考え方です。もちろん、現在のAIの中心はディープラーニングなのですが、それだけではできない部分もあります。なので、別のAIの手法で補うという研究をしてきました。先ほど申し上げた生成AIと組み合わせるというのも、新しい方向で結構研究されていて、我々も手掛けているところです。
02
「最近の生成AIは、まさに創発だ」との指摘もある

―蟻や蜂の群れが動いていくのを、AIでどういうふうに再現するのでしょうか。AIが進化していくというのは、どのように着目されてそこに結びついたのですか。
魚や蟻とかの進化もそうですけど、誰も神の視点は持っていません。それなのに、群れとして集まってくると、賢く問題を解いたり、賢く生き残ったりします。こういうのが、創発と言われているのですが、この創発という現象がどうして起こるのかというのは、まだはっきりとは分かっていません。あるレベルを超えると創発して、なぜだか問題が解けてしまうということがあります。その現象をできるだけ再現して、最適化やAIに使うというのが一つの考え方です。
「最近の生成AIは、まさに創発だ」と言っている人がいて、パラメーターの数やデータの量がある閾値(動作や意味などが変化・変動する境目となる値)を超えた瞬間に、今まで解けなかったと思っていたことが急に解け出したりします。それも数が増えた時に臨界値を超える創発という考え方です。そこにある程度つながっていきます。
―最終的には超知能(ASI:AIやAGIを超越した知能を持つとされる人工知能)と言われるものになっていきますか。
そうですね。それが今のやり方でできるかどうかは別として、たくさんの蟻が集まって作る巣は超個体(多数の個体の群れが一つの個体のようにふるまう生物集団)と言われています。同じように神経がどんどん増えてくると、知能を越えて超知能というレベルになるという考え方があります。
「最近の生成AIは、まさに創発だ」と言っている人がいて、パラメーターの数やデータの量がある閾値(動作や意味などが変化・変動する境目となる値)を超えた瞬間に、今まで解けなかったと思っていたことが急に解け出したりします。それも数が増えた時に臨界値を超える創発という考え方です。そこにある程度つながっていきます。
―そうすると、AIとAIが自動的に創発しながら学習していくようなモデルになるのですか。
それを今やろうと試みている会社もあります。OpenAI(米国サンフランシスコに拠点を置く、AIの開発および普及を目的とした非営利研究機関)もそういうことを言い出しています。将来的には、多くのAI開発企業がそれを目指すのではないでしょうか。
―元OpenAIの方が、「2027年にはプログラミングコーディング(プログラミング言語を用いてソースコードを記述する作業)で80%の信頼度が出て来る」と発言されています。伊庭先生はどう思われますか。
そうですね、ただ、そこにはある程度懐疑的なところがあります。もちろん、多分できる部分もあるでしょうけれども。それが人間の知能を越えて行くのかと言うと疑問です。やはりまだ人間でないとできない部分があります。それが今やっているLLM(大規模言語モデル)の延長だけではできないのではないか私は思っています。
コーディングとか専門的作業のある部分は、恐らくできる可能性があります。しかし、本当に人間臭いところ、例えば直感とか想像力とか、その辺りも全部できるかと言うと、難しい気がします。
―やはり、LLMだとどちらかと言うと確率的なアプローチです。単語の次にどういったものが来るかということがあります。プログラミングも同じような解釈で行くので、ある一定程度は行くと思うものの、人として共感するとか、人に対する思いやりは、なかなかAIでできない部分なのではないかと思っています。伊庭先生は生物学から入って来られているので、延長線上にはそうした世界が見えているのではと思います。いかがでしょうか。
生命としての生き残りみたいなものが、もし実現できるとまた別のフェーズができてくるかもしれません。生命は別に賢くなるために生きているわけではなくて、生き残るための結果として進化しているだけなので、そこはまだ全然実現できていないと思います。
―そうですよね。そうすると、AIにとって生き残るための脅威とは何なのでしょうか。人としても動物にしても、すべて環境に適応して生き残っています。AIは計算機の中にいるものなので、それが何らかの脅威とか、環境が変わることを自己学習でできるのかなと思ったりしてしまいます。
それはできないですよね。身体がないし、知ると言う概念を理解していませんから。だけど、例えば増殖みたいに自分を増やすのはどうでしょうか? 利己的な遺伝子(自己の生存率と繁殖率を他者よりも高めようとする遺伝子)をご存じかもしれません。進化論の言葉で言うと、遺伝子が本体で、身体は遺伝子の乗り物にすぎず、遺伝子がただ単に自分自身を利己的に増やしているだけだという考え方です。その考え方に立つと、多くの生命現象や進化を説明できます。もしも、AIが同じように、意識と言って良いのか分かりませんが、自分自身のある種のコピーを認識して、それをとにかく増やすことだけが自分の目標だと見なしたりすると、一種の進化みたいのがコンピュータの中でも出てくるでしょう。
まあ、ウイルスみたいなものです。でも、今のLLMでは恐らくそれはまだできないでしょう。SFみたいな話みたいですね。
―伊庭先生の場合は、LLMと進化計算、群知能など色々な合わせ技で、研究をされているという感じでしょうか。
はい、そうですね。メインは進化と創発です。
03
進化計算で新幹線のフォルムも構成できる

―伊庭先生は、メタヒューリスティックスという言葉をお使いになられています。これは、どのような意味なのですか。読者の方に簡単にご紹介ください。
これは、生命現象や人工生命の考えを用いてAIや機械学習における最適化をするアプローチで、要するに何か問題を解くために生物学的な考え方を利用する技法です。例えば蟻、蜂や魚の群れがその代表例です。ある種の物理現象もそれに相当します。その技法を用いると上手く最適化が解けることが分かっていて、こうした問題解決法を総称してメタヒューリスティックスと呼んでいます。これはAIでもともと使われていたヒューリスティックス(問題解決のための発見的な知識、いつもうまくいくとは限らないが大体うまくいく)を拡張した考え方です。
―伊庭先生のホームページでは新幹線N700系のフォルムも取り上げられています。その場合、フォルムはどういった形で作り出していくのですか。
新幹線の場合、フォルムとは先頭の形です。それがどういうのが良いかは、一概には言えません。例えば、風の抵抗も重要ですし、あまり抵抗ばかり考えると、今度は人を乗せられなくて集客が上手く行かなくなります。そういう幾つかのパラメーターを考えて、最適化すべきゴールがあります。
色々な人が様々な設計でフォルムを考えるのですが、それぞれの指標で良さ悪さがあります。それをまず大量に考えて、その中である程度ランク付けをします。進化計算においては、選ばれた親が子供を産んでその次の世代を作るわけですが、その時に単にフォルムをコピーするだけではなくて、良かったフォルム同士のある部分を掛け合わして、一部を交換します。これが、生命でいうところの有性生殖(親と異なる遺伝子を持つ新しい個体を生み出す方法)みたいなものになるわけです。さらに、あるものを突然変異で変形して形を変えるという無性生殖のようなことも行います。
最初の世代があったとすると、その中でより成績が良いものが子供を沢山産んで、より生き残りやすいようにして次の世代を作ります。そのときに単にコピーするだけではなくて、有性生殖で親の良いところを掛け合わせて子供を作るとか、親の一部を変形させて突然変異して次の世代を作のです。生命が次の世代を生成するのと全く同じなのですが、そうすると次の世代に少しずつ親の良いところを受け継いで、親のある部分を少し変えたものが出てくるわけです。それをどんどん繰り返すことで、集団として見ると全体の成績が段々と上がっていくというのが進化計算の考え方です。実際に新幹線で数式を立てて一生懸命計算して設計するよりも、最初に思いついた幾つかを進化計算の考えで構成していくことで良いものができてきた、というのが新幹線のフォルムの成功例です。
―新幹線や飛行機の翼だと、風洞実験を行い大量のデータを得ると思います。それら一つひとつのデータを取り合わせながら進化していくという解釈で良いですか。
その通りです。重要なのはランダムであることです。どれが良いかというのは、前もってわからないのです。これをどんどんやっていくと、良いものが実際に出て来ます。生物の進化と同じです。それを使った計算手法というのが進化計算です。
04
進化計算により、想像を越えたものが生み出される

―進化計算を含めた形でAIがどんどん進化していき、良いものは形が変わっていくというのは、正解のない世界ではないですか。これはある意味、AIが想像力を持っていると言い換えても良いのでしょうか。
進化の面白い点は、人間が思ってもみなかったものを設計するというところです。生物でもそうなのですが、カンブリア紀(地球の歴史上最初の時代)に人間からすると想像できないような生物進化が幾つも起きました。例えば、眼が5つある生物とか。ロボットも同様です、機械工学の先生だったら絶対設計しないような設計をしても動くことがあったりします。その辺りの面白さがありますね。だからそこはある意味想像力だと思うのですが、単にデータからの学習だけではできないかもしれないのです。
―人だとどうしてもバイアスが入ったりしますが、AIの世界だとバイアスが入らずにできてしまうのかもしれません。それが超知能みたいな形で人間を凌駕する世界が、いずれは来るかもしれないです。伊庭先生はどうお考えになりますか。
私は、ゲームAIの方もやっています。有名な話ですが、Google DeepMindがコンピュータ囲碁プログラム「AlphaGo(アルファ碁)」を開発し、その後囲碁の王者を打ち破りました。その「AlphaGo」が囲碁を打つ場面を囲碁のプロ棋士が最初に見た時に「これではプロには勝てるはずがない」と思いました。「AlphaGo」が勝った後でも、「これが本当に囲碁なのか」という有名な言葉も発せられました。要するに、囲碁ではない世界で戦って勝ったというわけです。それは、まさに人間の知能を越えているという意味では超知能と言えます。
その辺りが確かにAIで実現される可能性はあると思います。難しいのは、説明可能でないというということです。それを説明してくれると、囲碁に対する理解が深まります。それは他の分野でも同様です。そこが今のAIの限界でもあるし、難しいところなのです。ただ、確かに超知能が出てくる片鱗は色々なところにある気がします
―良く言われるのは、AI自身が論文を書いてノーベル賞を取れるまでになるだろうという話です。伊庭先生は、どう思われますか。
論文というのは、実は非常にテクニカルなものなので、ある程度訓練をつめば執筆できます。ただ、ノーベル賞を取るとなると全然レベルが違います。論文を100本書けばノーベル賞を取れるというわけでもありません。
だから、今まで人間にしかできないと思われていたことがAIでできたので超知能ができたという話があるのですが、それは逆に人間の業が実は簡単な作業なことが分かっただけかもしれません。事実、論文を書くのはその訓練を積めばできることであって、別にそんな大したことではなかったかもしれないのです。これは経験上の皮肉もこめて言っていますが。別の意味で言うと、人間でなければできないものも確かにあって、その辺りがAIに本当にできるのかが重要です。つまり、本当に人間しかできないことをAIと協働して模索することが重要だと思います。
―ありがとうございます。伊庭先生のホームページを拝見すると研究分野が6つぐらい挙がっています。それらを同時並行で進めている感じなのですか。
今は、生成AIと進化計算を組み合わせるところが中心の1つですね。あとは、応用としてロボットの研究も企業と一緒にやっています。医療データやX線解析への応用研究も行っています。ただ、私がメインでやっているのは、あくまでも進化と知能の創発です。それを使えるような分野への応用に関して、生成AIが今使えると思っているので、その辺りの研究を行っています。
05
LLMを応用し、ブラックボックスを最適化

―LLMは汎用性があり、素晴らしいものだと思う一方、どうしてもプロンプトを入力する人に結果がかなり依存してしまうと思います。効果的なプロンプトを生成することができれば、すごく便利だと思うのですが、どういった手法で取り組まれていますか。
これは、ある意味最適化の非常に単純な応用例です。プロンプト自体を最適化のターゲットにして、その入力でLLMから出力されたものと望む回答を比較します。上手くできていれば成績が良くて、そうではないのは悪いとして最適化すればよいのです。ただ、それだとそのプロンプト自体は作っているLLMに依存するので、もう少し中身のプロンプト、これをソフトプロンプト(人間の言葉ではわからないところのプロンプト)と言うのですが、実際のベクトルとか高度な内部表現になっているところまで最適化すると結構面白いことができます。
ただし、この方法だと公開されていないところもあったりするのと、応用分野が割と限られます。やり方としては今までのブラックボックスの最適化とある意味同じ問題になってきます。そのブラックボックスがLLM自身でもありやや扱い難いことがあります。それこそLLMはすぐに嘘を言ったり、新しいバージョンが出たら全く今までのが通じなくなったりするので、研究がやりにくいのです。それでも、ある意味ブラックボックスの最適化としては、非常に素直な問題ではあります。
―伊庭先生は、最近LLMをご活用されているという話ですけれど、自前で組むのですか。
もちろん自前で組むことはありません。公開されているものを自分でファインチューニング(既存のAIモデルを調整してタスクに特化させる手法)しています
―何を使われているのですか。
Chat GPTがメインです。あとは、Geminiです。我々はAPI(Application Programming Interface)でプログラムを組んで色々なことをやらないといけないので、基本的に公開されていないと使いにくいからです。他には、ディフュージョンモデル(拡散モデル:画像データ生成分野で利用されている生成AIモデルの一種)みたいな画像の類も利用したりしています。
.webp)
_%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_2x.webp)

_%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_2x.webp)
