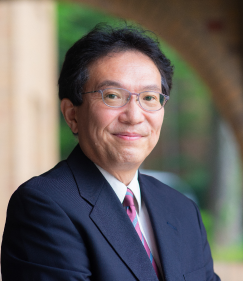
東京大学大学院情報理工学系研究科・電子情報学専攻 教授
伊庭 斉志 氏
PROFILE
01
仮想空間の中で進化計算ができたら面白い

―ここからは、話題を変えたいと思います。伊庭先生は進化計算というか、生物学から入られています。最終的にAIが人の感覚に近づくためには、やはり五感が必要になってくると思います。センサー系とかも研究領域に入っているのですか。
私は手掛けていないですけれど、ロボットを研究していたときに、センサーの分野で共同研究をやっていました。ただ、仰るように身体性がAIにはとても重要だと思うので、今後そういうのを上手く取り込んでいく研究は必要ですね。
―米国半導体大手のエヌビディアは、フィジカルAI(現実世界の物理法則を理解した上で、環境や物体と直接に相互作用しながら動作するAI技術)を打ち出しています。仮想空間の中に現実世界を作り出して、その中でシミュレーションするという動きがあります。そうすると実際の空間では、センサーロボットやセンサーが一定量の嗅覚や嗅覚を入れて自己学習を生成してやるのも、多分可能になって来そうです。どう思われますか。仮想空間の中でそういった進化計算をするというのは。
それは、まさに面白いですよね。元々が仮想空間上で人工生命体を作るところから研究が始まっています。なので、一番重要なことかと思います。そこの中でAIがどう考えて、どう振る舞うのかというのは、実際にやってみないとわからないところがあるわけです。その辺りに非常に夢があります。
たとえば、今よく研究されて、われわれも実験しているのは、人工生命が仮想環境で実世界と同じような物理条件やセンサー入力があるときに、どのように進化していくか、ということです。それも単体で進化するのではなく、複数の人工生命体が互いに影響を及ぼしながら進化していくモデルです。これを共進化というのですが、その結果として、異なる個体間で競争が起こったり、相手から搾取する寄生が生じたりします。さらに進化していくと、互いに協調していく個体が進化していくことが示されます。これは現実の生物とある意味同じですが、まったく違った道筋の進化が起こることもあります。このようなことを追求していくと、AIや複数のLLM同志の協調や共進化などのテーマにつながり、非常に興味深いと思います。
―まさしくエヌビディアは、AIカンファレンス「GTC2025」でフィジカルAIのもたらす世界を公表しています。今までは自動車の領域で、EV(電気自動車)や自動運転の車を開発するにしても、基本的には物理情報として集めないといけませんでした。それをある一定量だけ集めてしまった後で、色々な気象条件を勝手に仮想空間の中で作ったり、ロボットに関してもさまざまな地形を作り出して、そこで報酬モデルをやったりとか、失敗することにより、また学習するとかしながらどんどん進化しているのを見ました。「これはすごいな」と思いましたね。伊庭先生の研究も、そういった仮想空間に入ってくると、非常にすごい動きをするのではないかと思ってしまいました。
その辺りは、ロボットや人工生命の研究者にとっては一番面白いですね。しかも、最近はそういうのが割と簡単にシミュレーションできるようになってきました。昔は、すごく大変だったのですがね。楽になった気がします。
02
小中学生向けにAIの入門的な教育を展開

―ロボットはそうですよね。やはり大きな設備がないとできませんでした。それが今では、最初に模倣だけやれば自己学習していけます。すごいと思ってしまいます。話題を変えますが、伊庭先生はAI教育にMind Render(VR プログラムを作って遊べるプログラミング学習アプリ)を活用されています。この辺りのお話を少しお聞かせいただけるとありがたいのですが。
これは、「情報」という科目が小学校から導入されるにあたり、その教育の補助になればと考えて始めたものです。どうしても「情報」だけでは生徒からすれば面白くありません。「情報の中に例えばAIみたいなものを入れましょう」ということに賛同してくださる先生方に協力いただいたわけです。
元々、Mind Renderは、小中学校向けの校外学習用教材のようなものです。ロボット学習みたいなのと一緒になっていて、アプリ上でプログラミングを学習するというものでした。それが、最近Nintendo Switch™で動くことになり、かなり話題になっています。その会社の開発者と、昔から金融関係で知り合いであったので、そのソース上に「今度はAIを載せましょう」ということで協力させていただいています。
実際には、その教科書を作ってAIの簡単な記法をプログラミングして、Mind Render上に載せています。例えばレーシングカーのゲームAI対戦とか、あとは簡単な強化学習や進化計算とか、人工生命のトリガープログラム(データベースにおいて特定の条件や事象において自動的に実行されるプログラム)などを勉強して、それを自分で改造してみようというものです。東大でも学部生の演習授業で使っています。
実際にはそういう形で、情報教育の中にAIの入門みたいなものができれば良いというので、いくつかの学校に協力していただいています。それが上手くできるようになればと考えています。AIの考え方については、恐らく小中学生も知っているとは思うのですが、データリテラシー(データを的確に理解し、その信頼性を評価し、適切に活用していく能力)というのもありますけれど、今度はAIリテラシーが必要になって来ます。AIに対してどう付き合うのか、AIの本質は何か…、それらを早いうちからある程度分かっていた方が良いと思い、その辺りの教育にお役立ちしたいという想いがあります。
―昔は情報教育の一環としてITの使い方を教えるという動きがありましたが、今はもうAIですよね。
AIをどう活用するかは非常に重要です。
―あと騙します。というか、もっともらしい回答をします。
AIは平気で嘘を付きます。そういう中でどう自分はやっていくのか、特に若い人がAIとどうつきあうべきかを学んでほしいと思います。
03
高校生向けには、実機ロボットを動かす教育実習も行う
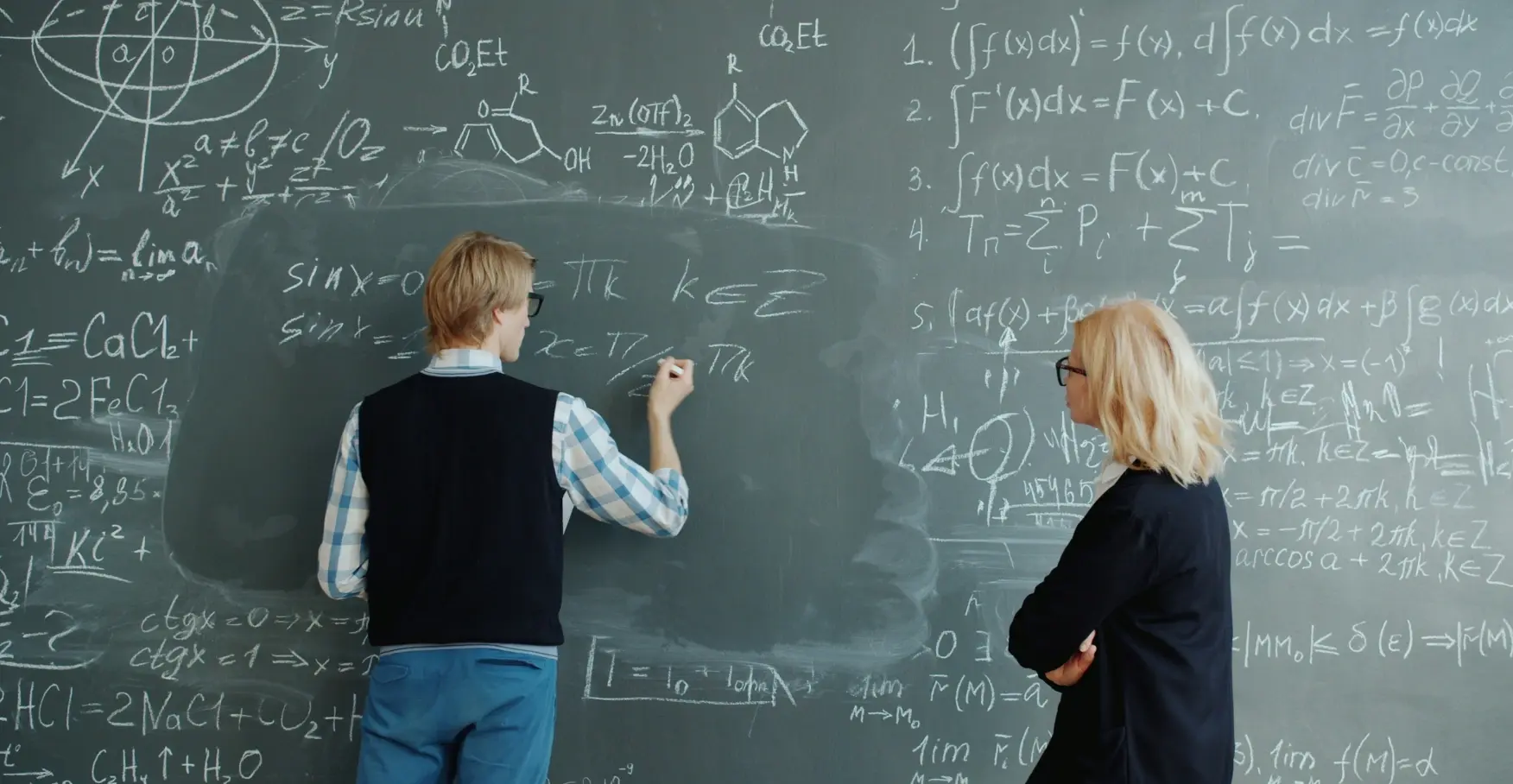
―それこそ本当に、動画や人の声、表示もフェイクで全部できてしまいます。実際、フェイク動画はもう溢れているので、本当騙されてしまいますよね。伊庭先生は教育実習として教室に行かれて教えられたりするのですか。
はい。埼玉県の大宮高校などに行きました。それはMind Renderではなくて、ロボットを学生自ら作るという授業です。そこで実際に教育実習の形でやらせてもらいました。
―いかがでしたか。何か、伊庭先生ご自身に気づきがありましたか。
やはりAIや進化計算の基礎を教えて、実機ロボットを動かすことをやりました。結構、学生も熱心に取り組んでくれていて、中には「どういう原理で動いているのかをもっと知りたい」と言ってくれた学生もいました。情報関係に関しては、「座学でやるよりも手を動かすことが、非常に重要だな」と改めて実感しました。
―実験機器は、かなり大きなAIのロボットだったのですか。
そうではなく、レゴみたいなAI学習キットを使ってヒューマノイドロボットを作りました。流れとしては、まずテキストでAIや遺伝的アルゴリズムの考え方などを学習する。次に、プログラムを見ながらAIの仕組みを理解する。その上で、ブランコのこぎ方や逆上がりを自動で最適化するAIロボットを作りました。これは、ブランコに乗った実機のヒューマノイドロボットが、足の上げ下げによりブランコを漕いでいくものです。授業の最初にはランダムに足を動かしていてうまく漕げなかったロボットが、授業の終わりころには重心の移動を学習して上手にブランコを漕がせるようになります。多くの生徒がこうした実機ロボットでのAIに感心していました。
―それは、いつ頃実施されたのですか。
6,7年前です。今はMind Renderの方に移っていて、ロボット実機での教育実習はやっていいません。
―そんな前からやられていらしたのですね。
それは、情報教育が必修になるということで、我々や企業の方、そして高校の先生も協力して始めた取り組みです。
04
AIに使われるのではなく、使いこなしていく姿勢が重要

―伊庭先生は教育の現場に立たれると共に、研究を通じて学生さんに教えられています。日本の若い人たちにとって、AIリテラシー向上の鍵は何だと思われますか。
日本独自かどうかはわかりませんが、やはりAIに使われず、むしろAIを使いこなすようにならないといけません。そこは特に重要です。日本は割と外国からのものに迎合するところがあるので、尚更注意すべきです。つまり、人間でなければできないこととか、批判的に考えるとか、人間らしさや共感、協調の必要性などを説いていくことが重要です。AIはある意味道具であるので、それを上手く使いこなすことです。使われたりはしないという心構え、その辺りは非常に重要なことだと思います。
―そうですね。最終的に人間力のある人が生き残ると思っています。AIが何でも手伝ってくれるものの、他方でAIリテラシーと一言で言ってしまうのは簡単なのですが、若い子たちからすると、AIがもう当たり前の時代になっています。私なんかはAIがない時代からいるので、基本的にAI前とAI後の変化は分かっていますが、今の小さい子供たちは、AIが自分のデジタルデバイス、スマートフォンに最初から入っています。これだと感覚が違うと思います。教育者としてその辺りを気づかせてあげないといけません。そこの難しがあったりしますか。
ありますね。例えば、レポートが一番顕著です。自分で幾つか論文を読んでレポートを書き上げるということは昔から良くありました。あるいは、大学院入試でも、自分のリサーチ計画を書くのが通例です。その場合、ほとんどの学生は生成AIを使って書き上げるでしょう。そこをどうするかが非常に悩ましいところです。
例えば、レポートの場合は逆手にとって、「生成AIで書かせてみたらこういうレポートが出来ました。それをサンプルとして与えるので君らがどう改良するのか、あるいは自分ならどう作成するのかを考えてほしい。」という課題を出すのです。それでまたAIを使うのかもしれませんが、少なくともまず自分で最低限は考えなくてはいけません。
恐らく学生は生成AIを使って来るでしょうし、逆に「使うな」と言ってもチェックできません。AIを使ったレポートと使っていないレポートがあって、使わないと成績が悪いとなると、それはあまりにも可哀そうです。だから、生成AIありきになって来たら、「それを越えろ」とまでは言いませんが、それを自分の中で消化してから提出しなければいけないと思います。でも、そこはいたちごっこなので、学生には言わないようにしています。
05
レポートにAIを活用するなら、その上を行け
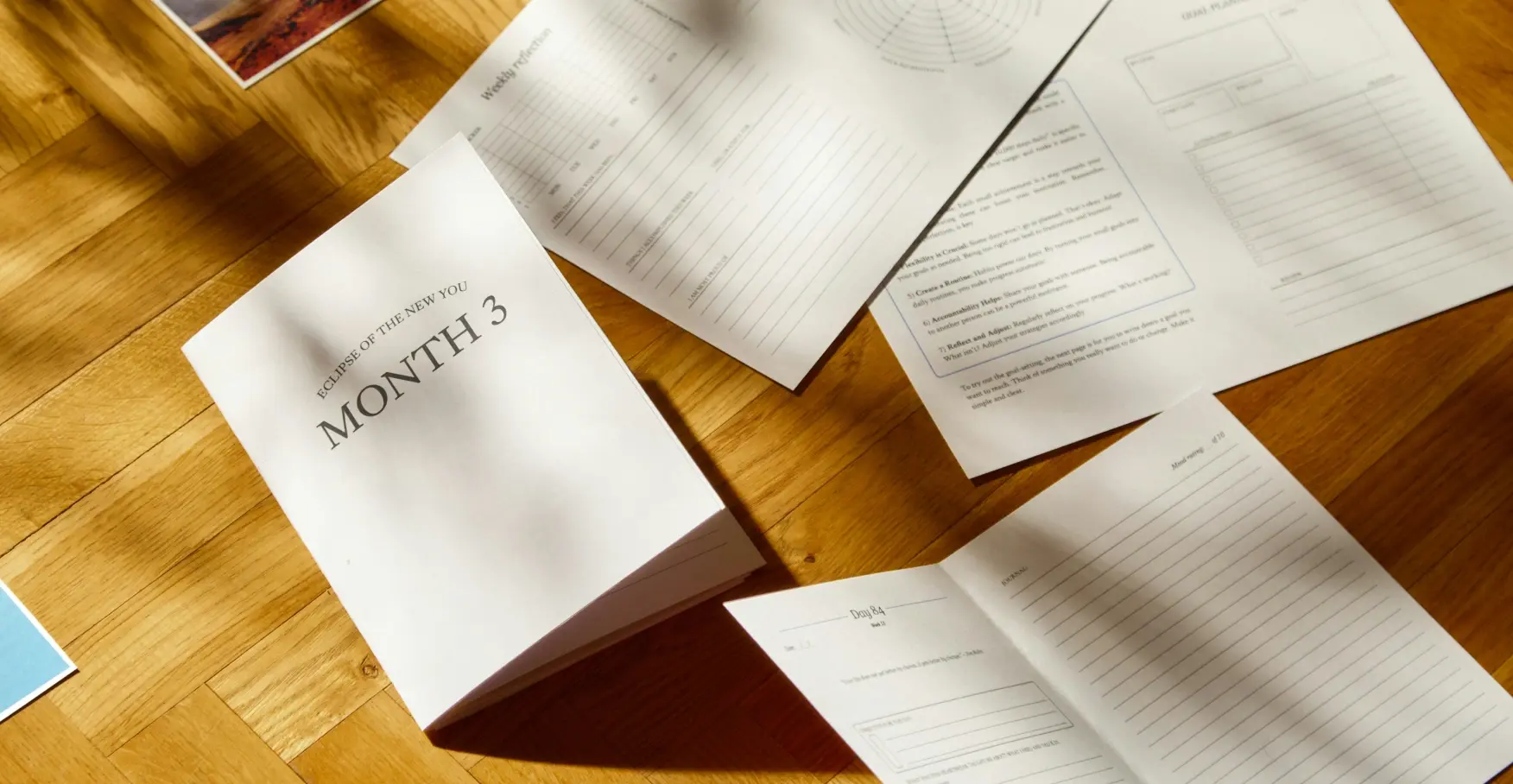
―伊庭先生は、レポートなどでAIを活用しても良いという推進派ですか。
もう止めようがありません。「活用しても良いけれど、その上を行け」と言うしかないですよね。
―基本的には、レポートを書く際に骨子などをAIで組み立てることができます。もちろん、オリジナルで考えた骨子に基づいて本文を書き上げてからAIで添削する、ブラッシュアップしていくという使い方もできたりします。そこを先生方がチェックできるのかというと、難しいと思います。そうすると、先生はどこに注目されますか。
それは、学生本人なりのオリジナリティーがあるかどうかです。入学試験や学期末試験であれば、試験の後に面接を行えば良いのです。「書き上げた内容に関して面接します」と言って。AIに100%書かせたのであれば、恐らく答えられないこともあるので、間違いなくすぐ見抜けます。なので、基本は後で面接して色々と聞くという形にすれば、生成AIを使っていたとしても、それなりに自分で勉強するはずです。それが一番なのかなと思っています。
―本当に昔は、リサーチに時間を掛けました。書籍やジャーナルを読むとかして。今はもう必要な資料や文献は、AIが教えてくれますからね。
参考にすべき論文も教えてくれますし、要約もしてくれるので読む必要もありません。それを評価するとなると、もう面接しかないですね。ただ、それも今後は生成AIにやられてしまうでしょう。実際、Zoomで面接をしようとすると生成AIが活用できてしまいます。
―AIで全部面談とかもできますからね。
少なくとも、現状では一対一だとまだ難しいです。耳やメガネに生成AIの機能を持ったツールを付けられるようになるとわかりませんがね。そこに至るまでの数年はまだ大丈夫なのではと思っています。
06
日本独自のやり方で戦っていくしかない

―ビジネス寄りのお話もさせてください。今、日本はAIに限らずテクノロジー、もっと言えば産業全般においても世界との差が広がって来ています。なぜ差が出て来ていると思いますか。
私はこの業界が長いのですが、色々な方々が保守的な考え方をしがちです。なので、新しいものを取り入れようというところで、まず遅れてしまいます。それは大学自体にも言えます。ある程度硬直化しているところがあったりします。企業の方もそうです。なかなか腰を上げなかったりします。国も同様です。外から言われてようやく取り組むと言う感じです。
あるいは、昔から指摘されているガラパゴス化(国内だけで独自の変化を遂げ、国際的な標準からかけ離れていること)も一因にはあると思います。もちろん、ガラパゴス化が一概に悪いとはいえません。日本独自のLLMがあっても良いのです。例えば、Sakana AI(サカナAI)をご存じでしょうか。2023年7月に設立された日本発の生成AI企業です。あの会社では、うちの卒業生など東大卒のメンバーが何名か活躍しています。元Googleの研究者であったデビッド・ハ氏とリオン・ジョーンズ氏(ChatGPTのもとになるTransformer論文の著者の一人)が日本で立ち上げた会社です。
なぜ、日本かと言うと、やはり日本には優秀な人材、特に若い人が多いからです。中国人留学生を含めてですがね。だから、ある意味、目の付けどころが良いと思います。しかも、彼らの考え方はかなり独自のAIです。とくに会社の名前から分かるように割と生物的なアプローチに取り組んでいて、私自身非常に面白いと思っています。それに続くようなAI企業、あるいはSakana AI自体がぜひ成功してくれることを祈っています。
「今すぐにGoogleやOpenAIに勝て」と言っても、それはもう無理な話です。ならば、日本独自のやり方で戦っていくしかありません。実際、そういうものができるはずです。少なくともLLMに関しては。あるいは、日本文化に根差すような独自の生成AIは、日本で作らないとできないのですから。やはり、米国的な思考ではないところに勝機があるのではないかと思っています。
―どうしても日本は、カルチャー的な部分で遅れを取っている気がします。チャレンジしようとしません。弊社もAIの研究部門を持っているのですが、残念ながらスタッフは全員外国人です。やはり、日本人はAIの知識や学ぶ姿勢が遅れています。失敗を恐れるところが、どうしてもあります。その点、外国人の方は取り敢えず行動を起こします。このままだとさらに差がついてしまうと思います。
日本はメガプラットフォーマーやOpenAIには、絶対太刀できないでしょう。ただ、その一方で、日本は島国だったこともあって独特のカルチャーを有しています。これが、AIと結びつくと非常に面白いと思います。
だから、Sakana AIでも、ラージではなくて複数のスモールランゲージモデル(小規模言語モデル)の組み合わせに挑戦しています。あと、Preferred Networksも東大卒の経営者が運営していいて、うちの卒業生もそこで活躍しています。そこでも日本独特の取り組みを推進しようとしています。そういう新たな企業が日本でどんどん生まれてくると面白いと思います。
07
AIの若手研究者や新進企業への手厚い支援が不可欠

―最後にビジネスパーソン向けの質問をさせてください。日本社会、もしくは日本の産業界が、AIを活用し世界と伍していくために、研究者や企業、政府が解決しなければいけない最重要課題は何だと思われますか。
若手の研究者や技術者、スタートアップへの手厚い支援です。大学で言えば、学者になろうという人が非常に少なくなってきています。それはある意味、企業も悪いのです。「大学で研究するよりも企業で研究した方が良い」と言っていますからね。そうでなくても、今や研究費がすごく不足していて、自由な研究が全くできなくなってしまっています。その辺りは、国や企業から大学に対しての支援を期待したいです。特に、若手の研究者や若い分野にです。AIもそうです。そういうものに対する支援が欠かせません。
それと同じように、若い企業という意味ではスタートアップやベンチャーなどの新進気鋭の企業への支援も重要です。それは、国が支援していくことになるでしょう。
―日本では国がAIに投じる予算は、ものすごく少ないです。OpenAIの開発予算にも及びません。
OpenAIと同じことをやっても勝てるわけがないのです。別の切り口に投資することです。それが、AIの若手研究者であり、AIの新進企業なのです。LLMを作るのとは、別な道を考えるべきだと思います。
―「では、何を選べば良いか」という目利きの部分が非常に難しそうですね。
若い人たちの感覚は重要です。単に、若い人は新しい物好きだからということでなくて、中には時代の流れをしっかりと見据えている人材がいます。そういう研究者に対して支援を集中投下していくことはとても大切だと思います。
それと、企業にも、大学と共同研究をして短期的な成果だけをむしり取ろうとするのではなく、若手の研究者を長期的な視点で支援していく姿勢を期待したいです。長い目で見ると、その方が双方にとっても良いと思います。
―私も同感です。産学で連携して特に若手が育つような環境を作っていかないといけません。どちらかというと、実を取るような仕事の方に若い人がいってしまっていて、AIの研究者が本当に少ないと思います。AIはこれから絶対になくてはならないものです。若い人材がどんどん出て来てもらいたいです。
そう思うのですが、優秀な学生はメガプラットフォーマーに行きがちです。今年も二人ほどGoogleに入社してしまいました。それでも、何人かが「博士課程に行きたい」と言ってくれています。最近は中国人が多かったのですが、日本人からも出てきました。状況は変わりつつあるのかもしれません。
―最近の若い人は、起業家精神も旺盛であったりします。すごいなと感心してしまいます。
そういう人もいますね。そうした人たちが、国からの支援を受けやすくなると良いと思います。
―主に東大ですが、エリート大学の学生たちに起業家精神が高まっています。今までであればJTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)と呼ばれる伝統的な日本企業に就職したり、外資系企業に入っていた人たちがスタートアップに行ったりしています。
そうですね。東大の修士課程や博士課程を途中で休学して、スタートアップで頑張っている人も何人かいます。上手く行ってくれることを願っています。
―そうした方々の活躍を含めて、日本が独自の活路を切り開いていくことを期待しています。伊庭先生、貴重なお話をありがとうございました。
_%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_sp_2x.webp)
_%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_2x.webp)
